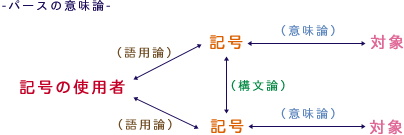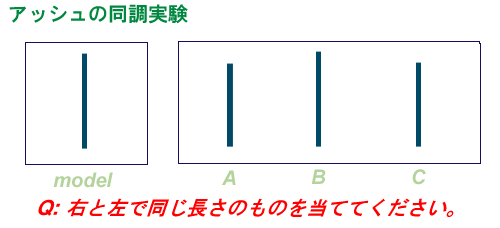人間は生まれたときから時間に沿って生きています。そしてそれは逆戻りすることはできません。一生、進み続けているわけです。発達心理学では特にこのことを「エイジング aging」といいますが、それはただ単に年齢が増えるというだけではなくて、身体的変化だったり、心理的な変化も絡んできます。
今回取り上げる「初期」というのは、いわば生まれる前を含んだもので、大体は赤ちゃんの時代を指します。このとき不思議なのが「座る→はいはい→歩く」のように、ある一定の順序で行動が出現してくること。これは言葉とかでもそうで、大体はじめて言う言葉は共通しています(バブリングといいます)。これには文化による差や、時代による違いなどは見られません。
これら行動はある特定の月齢範囲で生じること、しかも、教えなくても出現してくることから、あらかじめ誕生前から生得的機構として成立していると考えられます。
言ってしまえば、発達の初期では遺伝的な要因が大きな割合を占めているのでは、ということです(ここで言う遺伝的というのは、遺伝子レベルの話ではなくて、あくまで説明するための概念と考えてください)。
発達心理学ではこういうのをよく双生児研究(つまり、双子を対象とした研究)で見てきました。双子、特に一卵性双生児の場合、遺伝的な要因はまったく同じであり、違うのは環境です。もし、この2人で現れてくる行動が異なるとしたら、それはたぶん環境によるだろう、と考えられます。遺伝的なものであったとしたら、同じようなものがもう1人にも現れなければならないからです。
二卵性双生児の場合は逆のことが成り立ちます。遺伝的には違うわけですから、もし2人に同じようなことが見られるならば、それは環境によるものだろう、と考えられるわけですね。
一卵性双生児を対象にした研究で多分一番有名なのがゲゼルによるもので、これは1人には早いうちから階段を上がる練習をさせておき、もう1人は少し遅らせて練習を始めると、先に始めた赤ちゃんより、あとから始めた赤ちゃんのほうが、階段上りをマスターするのが早いというものです。
ゲセルはここから「生まれる前から行動はプログラムされていて、環境はその方向性に影響与えるだけ」という「成熟論 maturation theory」を唱えます。
しかし、すべての行動がプログラムされている、と考えるのはある意味無理があるのはすぐに理解できるでしょう。
それに、他の心理学分野が述べているように、人は環境との間の相互作用の中で生きています。行動主義で有名なワトソンの「私に12人の子供を与えてくれれば、どのような人間にでもできる」という極端な環境重視主義は別として、それによって行動が変わったり、制限されたり、生まれたりすることもわかってきました。
それは簡単な例でもわかるでしょう。たとえば、雛鳥が1日くらいの間に見たものを親と思う「インプリンティング(刷り込み)」なんかがいい例です(人間ではないですが)。
このように発達の初期に起こった環境との相互作用が後の発達の方向性を決める現象を「初期経験」と呼んでいます。人間を対象に研究することはかなり難しいことですが(倫理的な問題もあるし)、他の霊長類を使った研究によると、誕生後すぐに母親から隔離され、そのような状態が半年も続くと、他の仲間に対し消極的になり、自虐的行為が増え、大人になった後も配偶行動や育児などにマイナスの影響が出てくることが示されています(ハーロウによるアカゲザルを使った実験による)。
もちろん、これをすぐに人間に当てはめることはできません。とはいえ、単純に遺伝か環境か、と考えるよりは、遺伝も環境も、と考えたほうが実にあっている、と今の心理学では考えられています。あとで出てくると思いますが「アタッチメント(愛着)」などが言われるのもそのためです。
さて、赤ちゃんは一般的に能力が低い(何もできない)と思われていますが、これは間違いであることが認知的なアプローチからわかってきています。
もちろん、各器官の機能はまだ完全ではありません。しかし、視覚はすでに動き始めているし(分解能で言えば0.5~1 c/degくらい。c/degはcycle per degleeで、視角1度の中でどれだけ見えるか?の単位。大人は64 c/deg)、聴覚に至ってはすでにお母さんのお腹の中にいるとき(だいたい26週くらいから)から音が聞けることがわかっています。
これらは一般にバウワーをはじめとする「コンピテンス研究 competence research」が明らかにしたことですが、赤ちゃんの能力はそんなに低くない、というより、考えている以上のものを持っているといえるでしょう。
たとえばに生後2日目の赤ちゃんに、まだ生まれる前に聞いていたであろう動脈の血流音を聞かせると、大泣きしていたとしても安静状態になって寝てしまう(聞こえている上に記憶している!)とか、ある程度複雑な音(日本の実験ではお腹の上から落語を聞かせていた(^^;))でもそれは見られるとか、ガラガラの鳴るほうに目が向く(=音源の定位ができる+選択的に注視できる)とか、かなり高度なこともできるのです(ただ、大人と同じかというとそういうわけではなくて、たとえば図形をどう知覚しているかということについてサラパッテクは誕生後1ヶ月くらいまでは図形の頂点や境界にばかり注意を向けていると述べている)。
こういうことがわかってから病院では病室の明るさを昼と夜で変えたり、刺激として音を与えたりするようになりました。
いってみれば、ここに身体的な発達が加わってくるわけです。最初はばたばたするだけだった運動が、筋力とかがついたりしてきて、ちゃんとしたリーチング(対象に向かって手を伸ばす。把握する行動)になったりするわけです。そこまでにたとえば3ヶ月かかったりするわけですね。